11月中旬
広島県県北、吉和。
谷にたちこめていた朝靄が晴れると、
河原はもうすっかり晩秋のよそおい。
初雪はもうすぐ、また来年・・・
- 湖と野池編へ
暦が秋に変わってからも暑い日の続いた今年。カラフトマスの遡上にも大幅な遅れが出たらしく、まだ産卵前の魚もチラホラと見られました。
10月
今度は秋の北海道へシロザケ釣りに。
前回訪問から一月半、忠類川はサケの遡上が本格化していました。重量級の引きを堪能!
忠類川ではカラフトマスを相手に。
例年に比べ遡上の遅かった今年、お盆明けの魚影はまだ薄かったものの、その分ファ−ストラン、第一遡上群の魚たちは元気十分!
夏の盛りにして水温は9℃。北の自然の厳しさを感じさせられます。
知床の宝石、オショロコマ。峻烈な流れの中から次々に飛び出して僕らを楽しませてくれました。
8月 お盆
僕らにとって実に七年振りの北海道。涼やかな青空の下、知床の川に竿を振りました。
まだ背の張っていない綺麗な魚体。
流れに返すと元気な尾の一振りで
瞬く間に流芯へ消えてゆきました。
TeamリポビタンD、目もくらむ断崖絶壁を行くの図。体格ウルトラマン並のRon君がモデルでは冒険のスケ−ルを正しくお伝えできないのが残念!
8月初旬
釣友Ron君と源流釣行。フライの僕に気を使ってこの日はルア−で釣ってくれたRon君、そのお気遣いが功を奏し、見事な尺ゴギを仕留めてくれました。体高も十分な逞しい体、是非ともこの秘めやかな谷に長生きして欲しいと思います。
7月
吉和のアメゴも本流筋では9割以上が養殖された放流ものです。残念な事ですが遊漁者の過半数の人が魚を持ち帰る現状ではいたし方ないこと。
昔からいた吉和のアメゴは斑点が薄く体高もあまり無かったとのこと。そんな原種が残る川と聞いて、支流のひとつを訪ねてみました。かなり厳しい沢登りの果て、なんとか一匹とご対面させてもらいました。
苔むして横たわる大木。
森に積もる落ち葉が完全に分解され土となるまでにも二十年が必要とされるとのこと、これだけの大木が土に還るには、どれだけの歳月が必要となるのでしょうか。偉大な自然の営みを思い圧倒されるばかり。
8月6日
加計近くの中流域で水遊び。今年最後の広島の川を満喫しました。
こちらは翌週、吉和の別の細流へ。杉とミズナラの混交林は昼間も薄暗く、独特の静謐さをもって僕らを迎えてくれます。
か細いこの流れ。腕のいい釣り人が魚を持ち帰ったなら一日で滅びてしまうでしょう。遡行の難しさと釣り人の良識だけが、この沢を守ってくれています。最後にここを訪れてから五年、僅か数匹ながらここのアメゴ達が元気で迎えてくれたことを嬉しく思います。
森に湧く水で喉を潤し、川伝いに下ります。
一年後、また訪れる時までしばしのいとま。
中国山地固有のイワナ、ゴギ。
外国の雄大な川で大きな鱒に引きずり回されるのも一興ですが、秘めやかな日本の渓で可愛い魚に出会う満足がそれに劣ることは決してありません。穏やかな時間。
この川には川沿いに道はなく、一旦入渓すると後は川通しに移動するしかありません。上流域では崖をへずったり高巻きを強いられる難所もあり、ちょっとした源流探検を楽しませてくれます。
6月末
ゴギの沢へ。この日は25cmの良型に出会うことができました。冷えたビ−ルで乾杯です。
6月中旬
再び吉和の渓。今回は峡谷を流れる細流の釣り。
湖への流れ込みから釣りあがり、1km足らずで右写真、魚切の滝につきあたっておしまいです。あたりに舞う飛沫肌に冷たく、爽快このうえない森の隠れ家。魚影は薄いながら、この日は二人で三匹の美しい魚と出会うことができました。
秋には痩せてしまうこの滝も、梅雨のこの時期はなかなかの水量(写真左下に立つ僕と比較してみて下さい)。滝の上に通じる道はありません。この奥に渓魚の楽園があることを願うだけで十分です。
6月初旬
県北、戸河内の渓に。吉和と同じくこちらにも太田川の源流をなす深い森が広がっています。
放流量は少なく魚影は薄い一方、自然繁殖した美しい魚に出会える確率の高さが川歩きを楽しくしてくれます。
5月21日
広島県北部、吉和の渓。五月晴れの午後、川面に垂れる若葉や藤の花にも陽光がふりそそぎます。
中国山地の渓は多くが3月1日に解禁しますが、直後は大勢の釣り師が詰め掛け、多くの魚が持ち帰られてしまうため、楽しい時間が過ごせないことがほとんど。五年ぶりに竿を振るホ−ムリバ−で嫌な光景を見るのは忍びなく、解禁後しばらくは川に立つのを控えてきました。そんなわけで5月も後半。人も魚も少なくなった頃を見計らい、懐かしい渓に。果たして予想通り、殆ど魚影も見ない日でしたが、凄烈な流れに、日本へ帰ってきたんだな、と改めて胸が熱くなりました。
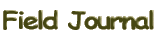 '06 川と渓流
'06 川と渓流
















