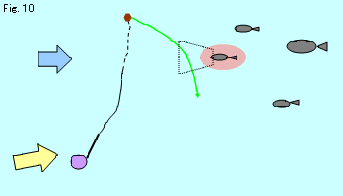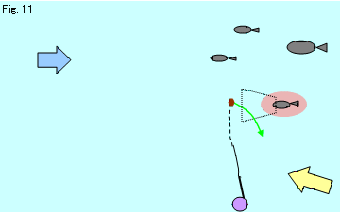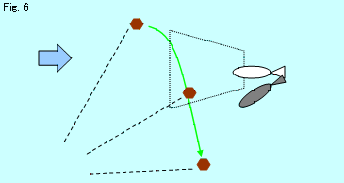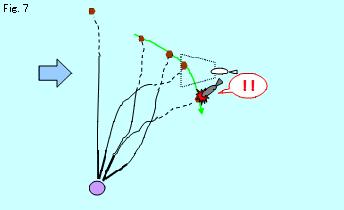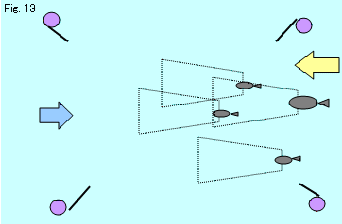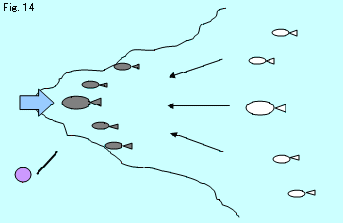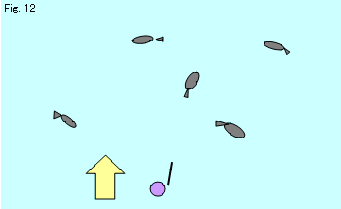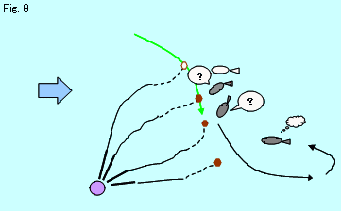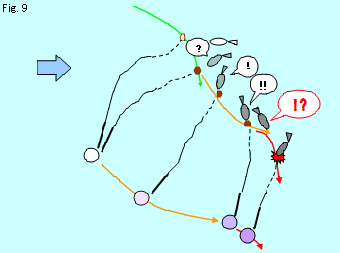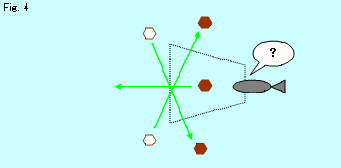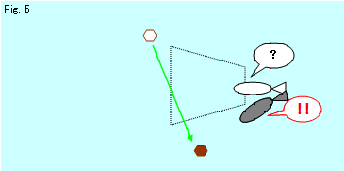ひきかえ、視界の隅をかすめて消えてゆく軌道はどうでしょうか。この攻め方ならば自分の立ち居地は魚の視線の延長上にはなく、スプ−クの危険を下げることができます。また誘いを開始する位地をリトリ−ブで修正することができるため、キャストにある程度の自由度が得られます。最後に、このように視界から遠ざかるフライを注視するためには、チヌは体を翻してフライと向き合う必要があります。この動作が魚の意識を捕食へと切り替える役目を果たしてくれるのです。
2015年追記:
釣りの様子を動画記録してみました。
-
以上、僕なりの発見を書き記しましたが、まだ新しいこのゲーム。いろいろなテクニックが発見される可能性を秘めています。是非とも皆さんも身近な場所でチヌと対峙してみてください。そして新しい発見があれば、是非ともお話しをお聞かせください。日本の誇るこの素晴らしいフライターゲット、その魅力をご一緒に掘り下げていきましょう。
- 戻る
今のところ、接着材にはSUが最適と感じています。SuperXよりもSUの方が粘着質で作業は面倒ですが、乾くと強く硬化し、濡れても弱らないように感じます。
乾燥を待ってラバーレッグの形を整えます。足の向きを調整するためにはピンセットを用い、一定の結びを左右対称に行ってゆくのがコツです。
効率よく作るコツは、5-6個のフライを同時に、骨格づくり、ボディ接着、足の結びという三工程を、一日一工程ずつ、まとめてこなしていくことです。
太陽と潮流を活かす
理想の誘いと喰わせ、これを実現する前提は全てが見えていることであり、相手の挙動が見えていないことには成立しません。ここで潮の流れに加え、太陽光の向きという要素(図中黄色の矢印)を考慮して考えてみましょう。
好ましいのは太陽が潮流とほぼ同じ方向から射している状況です。この場合、図10に示すように太陽側に立つことで魚をサイトすることはたやすく、また魚から発見されるリスクは大幅に低減させることができます。潮上から、快適にラインをコントロ−ルできる範囲で極力長い間合いをとり、魚へのプレッシャ−をかけずにアプロ−チすることが可能です。
対して潮流と逆方向から光が射す状況ではどうでしょう。潮上に立つと逆光でのサイティングとなり、魚からは順光となるためゲ−ムは難しくなります。この場合、極力太陽を背にできる位地にポジションを取ることが常套手段となりますが、潮上に頭を向けた魚を側面、比較的近い立ち位地から狙う構図ゆえ誘いは短くなりがち。難易度は高まります。
川の釣りの達人とは、例外なくメンディング技術に長けた人であると思います。いかにキャスティングが巧くとも、優れたフライを巻く技術があろうとも、賢い鱒に口を使わせるためには水面でのラインコントロ−ルが不可欠です。
ウェットフライの釣りを想像してみてください。ナチュラルドリフトを軸におきながら、条件次第ではラインスラックを与えてフライの沈下を促し、または流れを拾うライン配置でテンションをかける。それら流水でのるテクニックがこのチヌ釣りではそのまま活きてきます。違いはこの釣りの場合、全てが見える、サイトで行われることだけです。
確実な喰わせ
チヌがもし明らかにしびれを切らし、フライに跳びかかる姿が目視できたなら、一瞬ラインハンドを静止してフライが口に収まるだけの僅かな余裕を与えてやるのが理想です。成長したチヌの口の中はご覧の通り固い歯がびっしりと並んでおり、そこにフックポイントを立てることは困難。フッキングが可能となるのは歯の内側か、外側の唇の部分。写真のように深くまでのみこむヤル気のある魚は稀ですが、まさに捕食するという瞬間、ほんの0.5秒程度、フライの動きを止めてやることでフッキング率を改善することができます。
チヌが興奮に我を忘れる時こそ、自分は冷静を守り、喰わせの間合いを作り出してやること。バラシを減らすうえで重要なポイントです。
流しこみ
図中、左側から潮が流れているとします。流れが一定に効いている条件のもとでラインに一定のテンションをかけてやれば、フライは下流側で円弧を描きながら展開してゆきます。この軌道を狙う魚の捕食テ−ブルの隅をかすめるように描くことができれば、Fig.
5で触れた誘いを効率的に演出することができます。しかもこの誘いはリトリ−ブによる動きではないため、魚と自分の距離を徒に縮める心配もありません。
この一連の作法は流水の釣り、例えばサ−モンを狙う釣りまさにそのものです。流れが強い場合ラインの腹にはドラッグがかかり始め、フライを不必要に加速させてしまいます。これを防ぐため、フライが魚の捕食テ−ブルに差し掛かる直前、メンディングによってラインを上流側へ打ち返してやります。そのうえで再度流れに乗せてゆっくりとフライを流しこみ誘いをかけてやれば、チヌは視界をかすめてながら自分から遠ざかろうとするエサに強い関心を示し、捕食行動を取ることが多いのです。
フットワークで誘う
視界を横切るフライに関心を抱き、体を翻して追尾を始めたチヌ。左図でいけば、チヌは体の右側面に流れを受けて潮下に流されながらフライを追おうとします。しかしフライはラインが伸びきるとそれ以上下流側へ流されることは当然ありません。チヌがこの段階までに十分興奮していれば、離れていこうとする対象に執着心を見せ、一気に襲いかかることもあります。しかし多くのチヌは持ち前の警戒心が勝り、そのまま下流へ泳ぎ去るか、やる気を失ってしまうことが多いものです。
チヌにスイッチを入れてやるためには、念入りな、長時間の誘いが必要です。届きそうで届かない距離を、追おうと思えば追える速度で逃げ続けるエサを演出する、それを魚との距離を詰めすぎることなく行うためには、図9のように自身がフライの軌道にあわせて移動することが効果的です。右に左に身をよじりながらフライをかじり追尾するチヌを、じっくり入念な誘いで焦らせ、いよいよ興奮が最高潮に達したその瞬間、大きくストリップを入れて一瞬フライを魚の視界から消してやる。ご馳走を見失ったかと焦るチヌは、フライを再び視界に捉えた瞬間、我慢ならず跳びついてきます。
話を戻します。潮流と陽光がぶつかりあう状況はサイティングを困難にします。特に朝日、夕陽といった入射角が低い光の場合は、それを背に受けないことには視界を確保することができません。左図でいけば、右下か右上にポジションを取ることを強いられます。また入射角の低い光は魚の前方視界を広げる効果も持ちます。彼らの視界に入らないよう細心のラインコントロ−ルを駆使し、自分に最も近い位置の魚を狙うことが鉄則です。大型の魚が奥に見えたとしても、それは縁が無かったと諦め、最も手前の魚だけを狙うことです。
一見特徴に乏しい干潟にも、よく注意すると水流が作る起伏があるものです。前述したように、食い気のある魚達は、満ちる潮に浸る干潟の筋に沿って乗り込んできます。また、引き潮時に魚がよく残るのも、干潟が一段深くなるブレイクライン沿いです。干潮時その位置を観察記憶しておくことで、魚がいやおうなく密度を高める通り道、左図のようなポイントを効率よく狙うことも可能になります。
テイリングを撃つ
流し込みによるテイリング狙いについて既に触れました。しかしこれができない状況、例えば潮流が弱すぎる、乱れている場合の対応にも触れておきます。
それは、魚を直撃することです。但し、穏やかに底をつついている魚にフライを落とすと、その水音でスプークすることは確実。大切なのは射程距離に入ったら、我慢して待つこと。そして魚が捕食に我を忘れ、尾で水面をバチャバチャと乱し始めた瞬間、その音に紛れてフライを打ち込むのです。うまく行けば、捕食スイッチの入った魚は鼻先に落ちてきたフライにここぞとばかり、即バイトします。これも興奮度の高い釣り方です。
これを回避する術がないわけではありません。太陽が東から昇り西に沈むことは世の理。そしてフィ−ルドでの水流は潮の干満を読むことでかなりの部分予測が可能です。これらを考え合わせ、太陽と潮流の向きが極力一致する時間帯を釣ることで、サイティングのフラストレ−ションは大幅に回避できます。フィ−ルドに立つ前からゲ−ムは始まっているのです。
ここまで読まれると、メンディングに苦手意識のある方には流水の釣りを敬遠したくなるかもしれません。確かに全く流れのない状況ならば、太陽を背にすることだけを意識すればよく、ゲ−ムは単純化できるようにも思えます。しかし繰り返しになりますが、海には程度の差こそあれ、必ず流れがあるものです。また実は、流水がもたらす大きなメリットもあるのです。
潮流がもたらすもうひとつの大きなメリットは、フライをターゲットから離れた場所に落とし、静かに流し込むことができる点です。既に触れた『流し込み』に、安定した潮流は欠かせません。
浅場で砂の中のエサを探すチヌはしばしば、頭を砂につっこんで一心不乱にテイリングをします。右写真はチヌのお食事跡ですが、そのようなお食事中の個体は視界が極端に狭くなっており、鼻先にフライを送り込まないと気付いてもくれません。かといって、頭上ドンピシャにフライを打ち込むと脱兎の如くスプークします。そのような状況では、あらかじめ距離を測りながら落としたフライを潮流に乗せて魚の鼻先へ正確に流し込むことが最善。流れなしには成立しない狙い方です。
ここまでの図解では常に潮流の存在が意識され、お気づきのように魚は潮に頭を向けて描かれてきました。他の魚と同様にチヌも、こと捕食を意識した個体は必ず、潮上に頭を向けているものです。つまり、潮の流れはチヌの向きを一方向へ整え、狙い易い状況を作りだしてくれるのです。
潮が全くない状況ではどうでしょう。勿論、太陽を背にできる限り、サイティングに苦労はないでしょう。しかし四方八方、てんでバラバラな方向を向いたチヌの群れは全方位に警戒網を張り巡らせており、アプロ−チすら難しい難敵なのです。潮流の中での釣りを僕が好む理由のひとつがここにあります。
カニフライ
フライの好みは人それぞれ。フィールドによっても異なるのが当然です。前項に書いたとおり、僕にとってはフェルトで作るカニフライが定番となっていますが、そのレシピを参考に記しておきます。
フックは管つきチヌ5号。ダンベルアイをウェイトに、フロロ7号をライターで焼いたアイ。ハックルを数本触覚として、ラバーコードをレッグとして巻きとめ、骨格は完成です。フェルトボディ(写真にポインタを当ててください)をSUで接着します。
ところでフライフィッシャ−ならほとんどの方が流水での釣りのご経験があることでしょう。そして流れの中での魚の行動、流れを利用したドリフトや誘いについて一家言お持ちではないでしょうか。
海の水も実は、風や干満の影響を受けて常に動いています。特にチヌが好んで棲む河口域では川の流れが明確に存在する場合もあります。フィ−ルドを広く浅い川に見立て、その流れを利することができれば、スレた渓魚に精密なナチュラルドリフトで迫るが如く、この釣りの成功率を高める助けとなります。ここからが本題です。
チヌの捕食スイッチを入れるのは視界から遠ざかる動きです。完全な止水であればフライをタ−ゲットの目の前から視線の遠くへ、図4で言えば左側へリトリ−ブすることが最も分かり易い方法ですが、これには三つのデメリットがあります。
まずこの場合、自分の立ち居地が魚の視線の延長上にあるため、キャストの時の動きが魚の視界に入りやすく、スプ−クさせやすいこと。次に、魚を警戒させない程度に遠く、かつ魚に発見してもらえるだけ近い距離にフライを打ち込むことの困難。またこれが最も大きな弱点ですが、視界の真ん中でその目線上を逃げてゆくフライは魚にとって驚きの要素がなく、結果じっくりと観察され、見切られてしまうことが多いのです。
前項で、このゲ−ムの基本技法は一通りご紹介しました。しかし冒頭で述べたように、100匹のチヌをサイトしても手にできる確率はせいぜい一枚か二枚です。なればこそ、如何にして一枚を確実に捕り、きわどい二枚目をモノにするか、研究と研鑽に努めたくなるのがフライフィッシャ−の性。僕自身まだ道半ばではありますが、自分なりの発見のいくつかをここに記しておきます。
折角の研究テ−マ、是非自力で試行錯誤を楽しみたい方はご覧にならないことをお奨めします。1シ−ズンを暗中模索し、何千というチヌに無視され、嫌われて何かを掴んだ後にご覧頂ければ、我が意を得たりと手を打って頂けるかと思います。
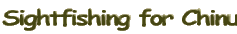 - 応用編 -
- 応用編 -