午後遅く、風が収まるのを待って再び西岸に。山の陰が落ち始めた浅瀬には森から吹き落とされた沢山の昆虫が打ち寄せられ、お膳立ては申し分ありません。
と、目の前、ほんの5mほどにモワッ、とライズ。そして間もなく、そばに浮かべた僕のカメムシ君にも、・・・モワッ!
夏に続き、今回もお世話になった弟子屈の釣り宿、鱒やさん。釧路川のほとりのログハウスは立地も雰囲気も抜群です。
ご主人の釣り情報はもちろん、奥様の手料理もほんとうにおいしく、道東の釣り拠点として申し分ありません。
70cm、80cmといった巨大な鱒が釣られたこともある屈斜路湖。しかしその茫漠たる広さゆえ、一匹をしとめるのは簡単でもなさそう。
そんななか近年注目を集めているのが秋から冬にかけて湖面に吹き落とされる森の昆虫たち、なかでもカメムシです。甲羅だけでも1cmを優に超える道産子カメムシ、最高にキモチ悪いですが、これを狙って大型のマスが接岸してくると聞けば、なんてゆうか、ねえ?
日中は前線通過の影響で強い東風が吹き戻し、湖西岸はちょっとした時化状態。
これをやり過ごすため風裏の東岸に入ってみましたが、こちら側はかなり遠浅な砂底。昆虫の気配も僅かで魚影も見えず、ただ平和な時間が流れてゆきます。
曇天の一日目は雰囲気絶好ながらアタリなし。まだ冷え込みが十分でなく、鱒の接岸が遅れているのだろうとの話。18度という表層水温は確かに高めですが、これだけ沢山落ちている昆虫にライズしないとは不思議です。
翌日は一転して快晴。上空に入った寒気のせいで気温は下がり、その点では期待のできる日になりそうです。Kimoo夫妻としばし、作戦会議。
このあたりのカメムシは腹部が赤っぽく、それがまた気味悪いのなんの!フライを巻きながらも背筋に悪寒が走ったくらいです。
釣りの最中こんなのが飛んできたらどうしよう、とビビっていたのですが、実際そこらじゅうで嬉しそうにブンブン飛ばれると、なんてゆうか、もう、どうでもいいです。
忠類での鮭釣りを楽しんだあとは西へ二時間、屈斜路湖へ。釣友Kimoo君夫妻と合流し、伝説のBigRainbowを狙ってみました。
周囲57kmという日本最大のカルデラ湖、1938年の地震の際には湖底から噴出した硫黄のために魚が死に絶えてしまったこともあったそうです。その後長い歳月かけての浄化、そして地元の方々の努力によってこの湖は再生を果たし、今では阿寒湖と並ぶ道東のフィッシングフィ−ルドとして人気を集めています。
今回は足掛け三日、40-43cmのニジマスを5匹釣ることができました。
特筆に値する釣果は得られませんでしたが、刻一刻と深まりゆく秋の気配、そこに息づく魚達の営みに触れられたのは、思い返す心にもじわりとしみる、極上の時間でした。車へ戻る道が森の闇に消えるのさえ気にしなければ、まだ明るい湖面にいつまでもフライを浮かべておきたい、そんな穏やかな夕べでした。
秋の北海道 - 後編
ちょっと派手目のライズは、エゾウグイ。二枚目とは言いませんが、まあ実直そうな顔をした好青年ではありませんか。
洋の東西を問わず湖の釣りとはこれ即ち退屈との戦い。竿が曲がる瞬間は、相手が何であれとりあえずハッピ−。ほめてます、一応。
そしてこちらは毛色を変えて屈斜路湖湖畔、夏にも訪れた仁伏(にぶし)の温泉宿。
ひわんだタタミやきしむアルミサッシ、さらには14型テレビのくすんだブラウン管、それらの全てが、僕の愛してやまない正真正銘の鄙びた湯治宿(何だそりゃ?)を主張してくれます。そして何といっても例の玉砂利の湯。ここにつからずして秘湯ファンは名乗れません。
恐るべし屈斜路湖仁伏保養所、
Tel. 01548-3-3058、ぜひ!
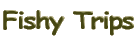
'06 秋の北海道 - 中篇美しい秋の彩りもそこかしこに。梢には冬支度を急ぐエゾリスの姿も。
なかなかトルクのある引きで楽しませてくれた屈斜路湖の初物。野生をとり戻した美しい体をしています。
この魚も、この後に釣れた他の魚もまったくジャンプしなかったのが少々残念でしたが、このパンパンに膨れたお腹を見れば、お食事の邪魔をした手前文句も言えません。そこに何が詰まっているのか、なんて野暮な詮索はナシということで。
腰まで立ちこんで釣りをしていると、澄んだ水の底に時折動くものが見えます。戦前の食料難の時代、蛋白源の確保にと移入されたウチダザリガニ。もともと冷水性であるため北海道の環境によく適応したようで、今では道内かなりの湖に生息しているそうです。
さほど滋養に富むとも思えない北の湖、昆虫のご馳走を期待できるのも所詮一時期だけです。にもかかわらず鱒が巨大化する背景には案外このザリガニの存在があるのかもしれません。













